高齢社員の増加による問題
2021年6月に「令和3年版高齢社会白書」が内閣府のホームページで公表された。高齢社会白書は、高齢社会対策基本法に基づき、1996年(平成8年)から毎年政府が国会に提出している年次報告書であり、高齢化の状況や政府が講じた高齢社会対策の実施の状況、また、高齢化の状況を考慮して講じようとする施策について明らかにしているものだ。
最新の高齢社会白書によれば、2020年(令和2年)の国内の労働力人口6,868万人のうち、65~69歳は424万人、70歳以上が498万人だった。労働力人口総数に占める65歳以上の割合は13.4%。下図のように1990年(平成2年)には65歳以上の割合が5.6%だったので、この30年で急激に高齢社員比率が増えていることが分かる。
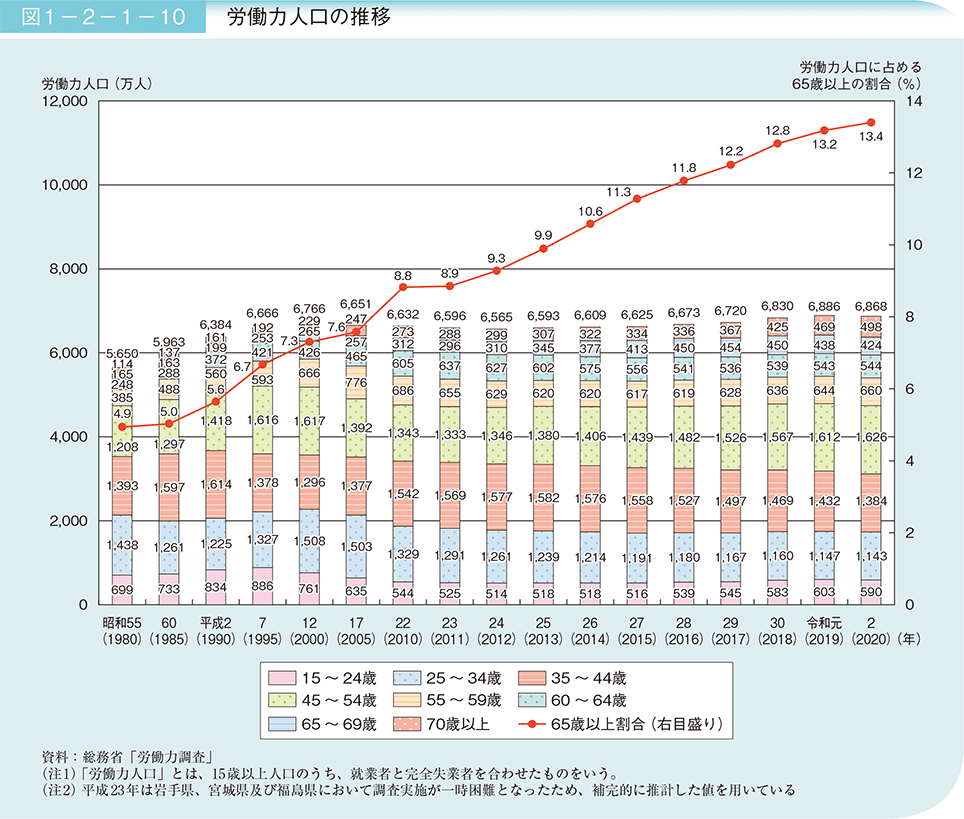
多くの企業が頭を悩ませる問題のひとつに高齢社員の増加がある。高齢社員だけが増加し、若手社員が増えないといったように社員の年齢構成がアンバランスな組織では、現実に「賃金の肥大化」「人事の停滞」「生産性の低下」などの問題が生じている。
■賃金の肥大化
多くの日本企業は、業績や職務ではなく、勤続年数や年齢によって決定される「属人給」を重視する傾向がある。「属人給」を重視した賃金体系では、高齢な社員ほど賃金が高いため、高齢社員の増加は賃金の肥大化を起こし、企業にとっては大きな負担となる。
大企業を中心に年功序列的な賃金体系を見直し、「職務給」や「業績給」など能力・成果主義的な賃金体系を導入するケースも増えているが、会社の規模が小さい場合、賃金体系の見直しはそれほど進んでいない。
■人事の停滞
見直しの気運が高まっているとはいえ、多くの日本企業は依然として年功序列の人事制度を採用している。年功序列の人事制度では、基本的に勤続年数に比例して社員は昇格する。高齢社員と若手社員のバランスがよい組織では、ベテランを追いかけるように中堅・若手社員が昇格し、定年に達した順に退職していくため、常に人事がよどみなく流れる。
しかし、高齢社員の数が多すぎると、中堅・若手社員が昇格するはずのポストが不足し、先がつかえてしまう。体力的な問題から以前ほど企業に貢献しなくなった高齢社員が高いポストにいる一方で、伸び盛りの中堅・若手社員は昇格できなくなってしまう。
■生産性の低下
高齢社員は総じてまじめであるといわれるものの、体力的な衰えを避けては通れない。そのため、肉体労働を必要とする企業での高齢社員の活用は難しくなる。また、長期間の勤務に疲れ、燃え尽きてしまう高齢社員も少なくないといわれている。どちらにしても、生産が向上することは期待できない。
リストラか有効活用か
上記のような問題に直面した時、企業は「高齢社員のリストラ」か「高齢社員の有効活用」かのいずれかの対応を迫られることになる。企業側からすれば、リストラによる負担の軽減が望ましいのかもしれないが、欧米企業に比べてリストラの経験が少ない日本企業は、関連会社への出向などによりできるだけ雇用を継続しようと努力することになる。
しかし、そのような状況の中、業績が予定通りに上がらない企業は新卒採用を控えざるをえない。その結果、企業における中高齢社員の比率は高くなるばかり。この状態は当面続くだろうと予想できる。
高齢社員を有効活用
高齢社員は、長年のノウハウと豊富な人脈を持つ貴重な存在といえる。その能力を有効に活用できる仕組みを作れば、高齢社員は若手社員の良い見本となるばかりでなく、経営者の重要な右腕ともなりえるだろう。
また、超高齢化社会の中で、企業には高齢者を多く雇用することが強く求められている。企業内の問題にとどまらず、社会的な命題として、高齢者を雇用することの重要性は高まっている。
高齢社員を有効に活用するために、企業が取り組むべきことは多々あるが、今回は企業にとって最も頭の痛い「賃金」に触れてみたい。
賃金体系の見直し
給料体系の再構築
高齢社員の賃金を適正にするための方法は、そもそもの基本的な給与体系を再構築するところから着手することになる。それはザックリと以下の2つの方法のどちらかになるだろう。
- 高齢社員専用の別建ての賃金体系の構築
- 高齢社員に限らず、全社的な賃金体系の見直し
着手しやすいのは上記1の方法。高齢社員専用の別建ての賃金体系を構築することだ。こちらの場合、賃金テーブルを若干変更するなどのわずかな実務で対応できるため、企業側の負担も少ない。実際、高齢社員の増加に悩む多くの企業は、高齢社員専用の別建ての賃金体系を構築している。
上記2の方法は、高齢社員に限らず、全社的な賃金体系の見直しを実施するため、多大な実務が発生する。全社員を対象にするため、賃金体系を抜本的に見直す必要があるからだ。しかし、抜本的な見直しは、現状の多くの賃金体系の問題を解決し、例えば、全社的な能力・成果主義に移行すするためのよい機会となることも事実。
どちらの方法を採用するかは経営者の考え方次第だ。
職務給の概要
「高齢者専用で別建ての賃金体系の構築」と「全社的な賃金体系の見直し」のいずれの方法をとるにしても、実際にどのような賃金制度を構築するかを明確に決定したうえで着手することが重要。ここから先は、高齢社員になじみやすいといわれる賃金制度である「職務給」について考えてみたい。
職務給とは、従事する職務の価値によって賃金が上昇する制度。職務給では、賃金決定の要素は、勤続年数や業績ではなく「職務」によって決定するため、例えば、同年齢、同キャリアでも研究開発に従事する社員と営業に従事する社員では賃金は異なる仕組みになっている。職務給は、転勤や部署替えが頻繁に行われる日本にはなじみ難いといわれてきたが、高齢社員の増加などを背景に注目を集めている。
高齢社員に適した賃金制度
職務給は、能力・成果主義的な賃金体系。これが高齢社員になじむと考えるのには理由がある。
従来の年功序列的な賃金体系では、基本的に勤続年数に比例して賃金が上昇する。この点こそが高齢社員の増加による賃金の肥大化の要因だ。まずは、職務によって賃金を決定する仕組みを作ることで、年齢による賃金の上昇を防ぐことが可能になる。
また職務給では、担当する職務の重要度・難易度によって賃金が決定される。そのため、高齢社員をこれまで養ってきたノウハウを生かせる職務に配置し、その職務に対する企業の評価を反映した賃金額を設定すれば無駄な賃金の上昇を防ぐことができる。評価基準を明確にすれば、高齢社員の理解も得やすくなるはずだ。
2つの目的を実現
職務給が能力・成果主義的な賃金体系であることは間違いない。とはいえ、単純に能力・成果主義的な賃金体系を導入することで、肥大化した賃金を圧縮しようとするのとは少し異なる。
単純に能力・成果主義を採用した場合、高齢社員の立場に立つと、優れたノウハウを持ちながら、体力的な衰えから十分に能力を発揮できず評価に結び付かないことが大きな不満になることが考えられる。
体力的な問題がほとんど関係ない職場でも問題がある。数十年という長い期間で養ってきたノウハウはそう簡単に失われるものではない。社内の高齢社員のほとんどが優れたノウハウを持っている場合、能力・成果で賃金の差を付けることが難しくなる。その結果、実質的に年功序列に戻ってしまうことさえある。
必要なのは賃金の圧縮と高齢社員の有効活用を同時に実現できる仕組み。この2つのテーマを実現できるものでなければ、賃体系を見直す意味は半減してしまう。そして、2つのテーマを実現できる制度の一つとして「職務給」の導入がある。
職務給の導入方法
職務の具体的な把握
職務給を導入するには、大前提として既存の職務を細かく把握する必要がある。また、どういった職務があるかだけでなく、「具体的な職務内容」「それぞれの職務に必要な能力」「その職務の責任」まで細かく調べることが必要。そのための手法はいくつかあるが代表的なものは以下の3つだ。
- 質問法:企業が把握したい項目をまとめた質問用紙を作成し、職務分析を行う職務分析担当者や部門管理者などに記入してもらう方法
- 観察法:職務分析担当者が実際に職場を回って、職場の様子や作業環境を観察・確認する方法
- 面接法:職務分析担当者が職務分析に必要な質問事項をあらかじめリストアップしておき、それを基に部門管理者などを面接する方法
職務の評価
職務を把握できたら、職務の相対的な価値を評価してランク付けする。そのための具体的な手法の代表的なものは以下の3つ。
- 序列法:それぞれの職務を比較し、複雑度・困難度・責任度などに応じて価値の高いものから低いものへとランク付けする方法
- 分類法:あらかじめ職務の熟練度・責任度などを基準に等級基準を作り、その等級基準に各職務を当てはめていく方法
- 点数法:職務の持つ責任度・努力度・作業条件などに評価基準ごとの点数を付けて、各職務ごとに採点し総得点によってランク付けする方法
市場賃金との比較
職務の把握、職務の評価によって得られた情報をベースに、その内容や性質を考慮して職務を分類する。そして、分類された各職務に対する賃金を決定する。この際に、市場賃金と比較することも大切。
各職務に対する賃金額は、会社の中でその職務がどの程度価値のあるものかで決定されるものではあるが、同じ業界の他社の賃金や同職種の賃金、同規模企業の賃金などとあまりにかけ離れていては社員の中に不満が生まれてしまう。客観的に妥当な範囲の金額であることが大切だ。



