デジタルトランスフォーメーション:DX
ここ数年、新聞やビジネス誌で『DX』という言葉を頻繁に目にするようになった。DXを「デラックス」と読んではいけない。DXは「デジタルトランスフォーメンション(Digital Transformation)」のことを指し、メディアの記事では「デジタル変革」と表現されることも多い。読み方は「ディーエックス」というのが一般的だ。
なにしろ『変革』なので、例えば「今の物流業務をIT化してコスト削減しましょう」といったレベルの話ではない。ITを使って、社会をデジタル化することにより、組織や社会そのものを変革しようというのが根底にある考え方だ。ウィキペディア(Wikipedia)によれば、もともとはスウェーデン・ウメオ大学のエリック・ストルターマン教授が2004年にその概念を提唱したらしい。
2004年といえば、米国Apple社がまだパソコンメーカーだった頃だ。今では社会変革のツールとなっているスマートフォンの代表格『iPhone』が登場するのがこの3年後の2007年である。「ITで社会を変革」というのに近い概念として、米国IBMが提唱した”スマーター・シティー”があるが、これは2009年から始まったもの。DX提唱の5年後だ。
ついでに、今現在、「組織や社会を変革したかもしれない」SNSについて調べると、Facebookが2004年、YouTubeが2005年、LINEは2010年に登場している。 ストルターマン教授が DXを提唱したとき、今では社会基盤として使われているこれらのITサービスはまだなかった。
経済産業省が定義したDX
概念だけ聞かされても、いったい何をしたら良いのか分からないのがDXだ。そもそも昔から言われていた「IT化」と同じなのかどうかも分からない。
2018年12月、経済産業省は、『デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)』を公開した。同年9月に経済産業省が公表した『DXレポート』における提言を基に、このガイドラインを出した目的は以下の2つだとしている。
- DXの実現やその基盤となるITシステムの構築を行っていく上で経営者が抑えるべき事項を明確にすること
- 取締役会や株主がDXの取り組みをチェックする上で活用できるものとすること
この中で「本ガイドラインでのDXの定義は次の通りとする。」として下記が記載されている。
企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること
引用:経済産業省『デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)Ver.1.0』
この定義では、企業が取り組むべきことが書かれている。DXの最終目的は「競争優位の確立」。そのためには単に製品やサービスを変革するだけでなく、企業文化までを変えて、取り組むべき覚悟が必要であることを示している。
販売とマーケティングのDX化
DXの最終目的は「競争優位の確立」。 そのためには、製品やサービスの企画・設計といった上流工程を変革したり、生産工程の変革、販売や流通の変革、保守や運用といった下流工程の変革など、さまざまな領域で「データとデジタル技術の活用」が考えられる。
前述のガイドラインを公開した経済産業省は、例えば『製造業DX取組事例集』のような取材資料の公開を通じて、日本を代表する大企業から中堅に至るまで、さまざまな製造業の具体的なDX化事例を紹介している。
製造業に関して言えば、世界的にAIやIoTなどの先端デジタル技術を活用したものづくりが広がり、過去の常識や既存ルールが大きく変化していることが背景にあるのだろう。さらに日本の製造業においては、世界一速いペースといわれる少子高齢化による労働人口の減少などによりデジタル変革が必須という側面もありそうだ。
ここではDXによって「本当に市場に変革を起こした」とされる、2つの小売業を見てみよう。2つの企業の共通点は「販売とマーケティングのDX化」だ。そして、10数年で既存の市場をごっそり奪ってしまった。
ZOZO(ゾゾ)
2019年9月、ソフトバンク傘下のヤフーが、ファッション通販サイト「ZOZOTOWN(ゾゾタウン)」を運営するZOZO(ゾゾ)買収を発表した。ヤフーは約4000億円もの金額を投じて、ZOZOを連結子会社化したのだ。ヤフーの収益は広告が主体だが、この買収により電子商取引(EC)をもう一つの柱にすることを狙ったという。
ZOZOは、2000年にインターネット通販を手掛けてから、アパレル販売を中心に急成長を遂げた。その19年後のヤフーによる買収直前、2019年3月期の商品取扱高は3200億円を超えており、ZOZOTOWNの年間購入者数は800万人以上と、アパレルの通販サイトでは圧倒的な1位だ。
ZOZOの驚くべき急成長は、まさにDXによって市場に変革を起こしたことが要因だ。もともとECの黎明期には、ファッションに代表されるハイタッチ商品の販売は、ECには向いていないと言われていた。そんな中でZOZOは、若者に人気のあるブランドを多く取りそろえることに徹底的に注力した。圧倒的なブランド数を揃え、そのうえでZOZOは翌日配送、7日間返品可能、実質値引きとも思えるポイント還元、等身大モデル試着の画像提供、コーディネート提案など、実際に試着できないという欠点を補って余りある販売サービスをITで実現した。
この結果、試着できないために通販には向かないとされていたアパレル市場においても、売り上げを急速に拡大することに成功した。それまで店舗を見て歩き、試着して購入する若者の行動を、ZOZOは一変させたのだ。まさにデジタルを使って変革を起こした。
Amazon.com(アマゾン・ドットコム)
デジタルで世界中に変革を起こした企業といえば、GAFAと呼ばれる4企業がその代表だ。GAFAは米国企業であるグーグル、アマゾン、フェイスブック、アップルの4社の頭文字を並べたもの。どの企業もITを活用したサービスを展開するためのインフラを提供していることが特徴だ。
ストルターマン教授がDXを提唱したのが2004年だと前述したが、米アマゾン・ドットコムが創業から6年間の大赤字期間を何とか乗り越えて単年度黒字になったのはちょうどその頃だという。今ではアマゾンが、その巨大なECプラットフォームを構築したことで、ユーザーはどこにいても何でも好きなものが買えるという環境が得られた。買い物に行くという「行動」を完全にデジタルに置き換えたのだ。米国の有名な大手小売業の破綻は、アマゾンが実践したDXによる影響が少なくない。
また、アマゾンは、「レコメンド機能」を実装したサイトの先駆者として知られている。アマゾンの商品のページには、「よく一緒に購入されている商品」や「この商品を買った人はこんな商品も買っています」といったタイトルのもと、関連が高い商品が掲載されている。まるで店舗の店員のように、個々のユーザーに応じて商品を推薦する機能をサイトに実装し、ユーザーの行動をさらに活性化する役割を担っている。これまでは、店員がその知識や経験から「こちらもいかがですか?」とやってきたことを、デジタルに置き換えたのだ。
最近、アマゾンが消費者の行動に変革を起こしてきた分野には、動画配信などのデジタルコンテンツの提供がある。映画などの動画を自宅で見るためには、これまではブルーレイディスクやDVDを購入するか、あるいは借りてくる必要があった。動画配信により「モノ」を買ったり借りたりするという必要がなくなり、デジタルに置き換わったのだ。
デジタル化で実現した「ロングテール」
デジタルを活用したアマゾンから生まれた「まったく新しい販売とマーケテイング」に、ロングテール戦略がある。これが話題になったのは、アマゾンがまだ「インターネット書店」がメインビジネスだった頃の話。下図がその考え方だ。
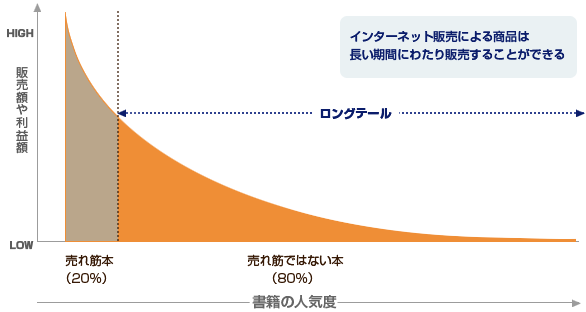
一般に、8割の売上を2割の優良顧客が生み出すことから、努力は全体ではなく、2割の顧客に集中すべきという論が主流をなしてきた。ニッパチという言葉は、マーケティングを知らない人でも聞いたことがあるはずだ。
従来の書店に置いてあるのは2割の「売れ筋本」。上図のように書籍販売額を縦軸に、横軸に売れた数順に商品を並べると、売れ筋の2割以下の部分、つまり売れ筋ではない本については長い尾のような形をしたグラフになる。これがロングテールである。
デジタルで自動化
1900年代の初め、イタリアの経済学者ヴィルフレード・パレートは、「パレートの法則」を提唱した。「80対20の法則」、つまりニッパチとして、ビジネス界において普遍的な経験則として広く知られているもの。経済やビジネスの世界だけではなく、自然界でも頻繁に見られる現象のようだ。ビジネスでは、たとえば次のようなことを意味する。
- 売上の80%は、顧客の20%が生み出す
- 売上の80%は、商品の20%が生み出す
- 売上の80%は、社員の20%が生み出す
- トラブルの80%は、顧客の20%が生み出す
2割の優良顧客を優遇するのは当然として、ビジネスでは残り8割の普通の顧客は「切り捨てられている」のが常識だった。その理由を端的にいえば、顧客とのコミュニケーションにコストがかかるからだ。営業マンの人件費や通信費、そして広告費等の経営資源には限りがある。限りのある経営資源をできるだけ効率的に配分し、コストに対して利益を最大化するには、2割の優良顧客に努力を集中すべきだという考えが有効になる。実はこれが、現代マーケティングの基本戦略そのものだ。
しかし、インターネットが登場し、コミュニケーションの構造は根本的に変貌を遂げた。コミュニケーションコストが、限りなくゼロに近づく歴史的転換を果したのである。Webサイトやブログを利用すれば、1人が数億人とコミュニケーションをとることすら可能になった。コミュニケーションが従量制コストだった時代はついに終わりを告げた。
このような状況で、「eマーケティング」というインターネットを使った販売とマーケティングが出現した。アマゾンは、書店ではコストに見合わないような「売れない本」を数多く売ることを可能にした。「売れない本」の売上を限りなく多くすれば、結果的に膨大な売上がもたらされる。
優良顧客を優遇しリピート化する戦略、あるいはターゲットを絞り込み、そのターゲットに集中する戦略といった現代マーケティングの常識は、すべて「従量制コミュニケーションコスト」の世界で構築されたものである。インターネットの普及がもたらした「コミュニケーションコスト“ゼロ”」の世界では、従来の常識は通用しない。
「ロングテール」では、従来の常識と異なり「絞り込まない」戦略が中心となる。そして、その絞り込まない戦略を実行するためには、「販売とマーケティングの自動化」の推進が必要となる。顧客への対応、すなわち販売とマーケティングをデジタルで自動化することで、人間ではコスト的に不可能であったニッチなニーズに対応できる状況をつくり出すことが可能となり、売上の絶対値を底上げする。
年に3冊しか売れないようなマニアックな本を書店に置いても、商売にならない。しかし、こういった潜在需要は無限に存在する。それを採算がとれるビジネスにすることを可能にするのがデジタル化だ。従来は3種類のベストセラー本を各10万冊売ることでビジネスが成立したが、アマゾンが実行したデジタル化では、コストをかけずにあまり売れない10万種類の本を各3冊売ることができた。リアルな書店が「捨ててきた」市場を、デジタル活用で拾い上げることが可能になった。
デジタル化により、販売とマーケティングを自動化すると、個々の販売活動はもとより、マーケティング活動とその結果がすべて確実にデータとして記録されることになる。この記録の分析結果をさらに自動的に次のマーケテイング活動に反映させることで、確実に売上を上げるための仕組みづくりができる。
従来の仕組みをデジタル化し、自動化した「コミュニケーションコスト”ゼロ”」の世界においては、ロングテールを主要な商材として扱うような、販売とマーケティングの革命が起きる。アマゾンはそれを実証してしまったのだ。



